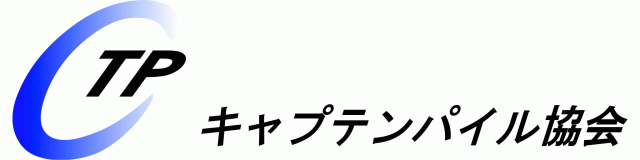変体かなの楽しみ
小田 初次,大末建設
この度の東日本大震災の被害を受けた方々に、心よりお見舞い申し上げます。
大末建設の小田と申します。
今回、コラムを書かせていただくことになりました。どうぞよろしくお願いします。
過去のコラムを拝見すると皆さん趣味のお話をされているようなので、私もちょっと特殊ですが、ここ10年ほどはまっている、変体かなの話をさせていただきます。

今は、ひらがなはひとつの音に対してひとつの字を決めて使われていますが、江戸から明治初期までは、この「は」の字のようにひとつの読みに対して複数の文字が当てられて使われていました。これを「変体かな」と呼びます。ひとつの文字に対して大体2字から3字が割り当てられていましたから、いろは48文字なので、150字位が使われていたようです。

それで、変体かなというものが使われているということを教えてもらい、本で勉強して読み始めたところ、これがパズルや暗号を解読するようで面白い。木版の印刷物でも字は続け字で崩してあるので、ひとつの字に対して、候補の文字が数種類あり、簡単には決められません。漢字もあまり使われていないでほとんどひらがななので、単語の切れ目が判りにくいのですが、前後の意味を考えながら文字や単語の切れ目を仮定しながら数行読み進めていくと、ある瞬間に今まで曖昧だったところがぴったりと嵌って文章が明快になる。これが結構面白くて、続けています。今まで読めなかったものが読めること自体がうれしいものですが、店に飾ってある版画や浮世絵に描いてある文字が読めると、結構いい気持ちになります。

最近では古文書を学ぶことがブームと言われています。講座や独習用の本もたくさん出ていますが、変体かなは、ひらがなが主なのでお手軽だと思います。興味をもたれる方がおりましたら、ぜひ一度試してみていただきたいと思います。
興味をもたれた方用に独習用の本の案内を載せてきます。
http://www.kashiwashobo.co.jp/new_web/pamph/pamph08.html
2011年5月